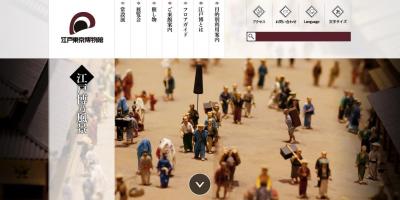大人の社会見学の新着30件
2015年11月10日 12:00
西洋文化との融合にて表現されたもの
東京都墨田区にある江戸東京博物館では、2015年12月6日までの期間、特別展である「浮世絵から写真へ -視覚の文明開化-」が開催されている。休館は毎週月曜日で、開館時間は9:30〜17:30(土曜日は19:30まで)で、入場は閉館の30分前まで。この展覧会では、浮世絵を初めとする絵と、幕末期に渡来した写真が絵と融合していた様を紹介している。幕末の人々も深い関心を寄せていた
幕末から明治の浮世絵を見ると、当時の人々が深い関心を寄せていたことがわかる。くわえて写真側も浮世絵を初めとする絵から影響をうけ、そのため絵と写真は、互いに影響を与えつつ面白い作品を生み出していた。そこには人々の好奇心や、新しい表現を手に入れたいという気迫にくわえて、江戸時代以来の伝統も見え隠れしていた。
展示会の見どころ
この展覧会には見どころが3つあげられる。1つめは、それまで日本で制作されていた浮世絵などから着想を得て作成されたものだ。浮世絵の風景画や、版本の挿絵にそっくりな写真が見られるほか、百人の美人を集めて撮影するという、昔から愛好されてきたテーマでの撮影だ。
2つめは、明治時代に入ると今度は画家が写真を参考にして、その人物そっくりな絵を描くようになった。この展示会では浮世絵師の小林清親や、日本画と洋画を描いた五姓田芳柳、写真師の江崎禮二らの作品を展示している。
3つめは、幻の技法となってしまった写真油絵である。写真油絵とは、印画紙の表面だけを薄く残して紙を削り取り、裏から油絵具で着彩するするため、繊細な技術が必要とされる。
この技法は横山松三郎によって1880(明治13)年ごろ考案され、弟子の小豆澤亮一に伝授された。
小豆澤は1885(明治15)年に専売特許条例が施行されるといち早く特許をとり、「専売特許」を掲げて制作を行ったが、緻密な作業を伴う画法だったため、近眼になってしまう。写真油絵は天覧までされるようになったが、1890(明治23)年小豆澤の死去とともに忘れ去られてしまった。
展覧会では日本の絵と写真のからみあう関係を、時代を追いかけつつ閲覧ができるという珍しいものとなっている。足を運んでみるといいだろう。
(画像はホームページより)
江戸東京博物館 特別展 浮世絵から写真へ -視覚の文明開化-
https://www.edo-tokyo-museum.or.jp/
-->
記事検索
特集
アクセスランキング トップ10
お問い合わせ