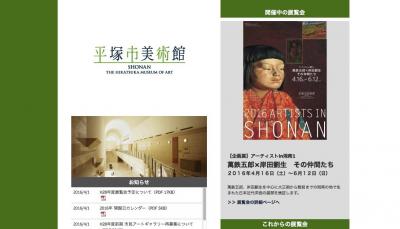大人の社会見学の新着30件
2016年4月22日 13:00
湘南が若い画家たちの縁を繋ぐ
神奈川県平塚市にある、平塚市美術館では2016年6月12日(日)まで企画展として『萬鉄五郎×岸田劉生 その仲間たち』の展覧会を行っている。この展覧会は大正期から戦前までの湘南の地で生まれた日本近代洋画展開の検証をするものだ。その中心にいた、萬鉄五郎と岸田劉生は、日本の近代美術を語る上で欠かせない人物となっている。湘南地方は、明治期に別荘や療養地として過ごすという独特な文化がうまれていたため、この2人は大正期を転地療養のため、湘南の地で過ごしている。
そのためこの2人を慕う若い画家たちも集ってくるようになったため、この地に多数の画家が住まったという背景がある。
1915(大正4)年、新しい表現を求める若い画家たちが「ヒュウザン会」に萬、劉生とともに参加している。第1回の展覧会は世間の注目を集めたものの、当初より会則も方針もなく発足した団体であったため、翌年の第2回展開催後に解散となってしまう。
東京での活動ののち
その後劉生は代々木に転居し、友人の肖像を次々と描いていくいわゆる「劉生の首狩り」時代へと入る。それから東京郊外の新聞者の赤土が目立つ風景を描き、1915(大正4)年、木村莊八、中川一政、椿貞雄とともに草士社を結成する。その後は都外の写生によってリアリズム表現を模索するが、体調を崩し肺結核となったため、1913(大正3)年療養のために鵠沼へ転居する。
一方萬は郷里である土沢に戻り制作に没頭するあまり、神経衰弱と同時に肺結核となってしまったため、茅ヶ崎に転居する。そのため2人は湘南で再び活動を始める。
1922(大正11)年小杉未醒、山本鼎らにより、春陽会が設立されると、萬および劉生は客員として参加をする。この2人の参加のため、2人に私淑していた原精一、森田勝、鳥海青児の3人も春陽会へと参加した。
やがて1927(昭和2)年に萬、1929(昭和4)年に劉生が亡くなるものの、この2人が湘南の地で他の作家に与えた影響は計り知れないものがある。
休館日は毎週月曜日で、開館時刻は9:30から17:00(入館は閉館の30分前まで)となっている。
(画像はホームページより)
平塚市美術館 アーティストin湘南1 萬鉄五郎×岸田劉生-その仲間たち
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/
-->
記事検索
特集
アクセスランキング トップ10
お問い合わせ